
「もうお片付けの時間でしょ!」
「さっきもう終わりって言ったでしょ!」
お子さんの遊びをやめてもらうときに、こんな声掛けするのにうんざりなんてママパパも多いのでは?
今日はそんなママパパの強い味方になる、『知育時計』のメリットを活かして、お子さんの自主性を上げるための、『知育時計』の選び方などについてお伝えしていきますね。
知育時計ってなに?
そもそも『知育時計』って何?
普通の時計と何が違うの?
という疑問が湧くかもしれません。
『知育時計』というのは、お子さん向けにわかりやすくデザインされている 時計の読み方や、時間の感覚が学べる時計のことです。
例えば、文字盤のデザインでは、時間や分の数字が色分けしてあったり、○時の数字と△分の数字の大きさを変えたり、長針・短針が表す範囲をわかりやすく表示したりなど、お子さんに理解しやすいよう、また楽しさも味わえるよう工夫されています。
子どもの時間の感覚はいつ頃から育つの?
大人にとっては、当たり前になっている時間の感覚ですが、お子さんにとっては、まだまだ時間という概念は未熟です。
「あと5分」と言ったら、大人は、大体このくらいという時間の予測ができると思いますが、お子さんは大体このくらいの基準になる感覚を知りません。
これから経験していく中で覚えていくものだからです。
とはいえ、お子さんが「時」の感覚が全くないのか?といえばそうではありません。
赤ちゃんにとっては、朝の日差しを浴びて、1日の始まりを体感し、そして、朝ごはんを食べ、次はお散歩やお買い物、お昼になれば、お昼ご飯を食べ、お昼寝をして、夕方になりだんだん辺りが暗くなってきて、夜ご飯、お風呂、就寝…。
そんな毎日の生活リズムを通して、「時間」という感覚を少しずつですが育て始めていくのです。
具体的な時間の概念「5分後」とか「30分後」のような、時間の長さという意識が芽生えてくるのは4〜6歳ごろと言われています。
この頃の意識の芽生えが、後々小学校へ行った時に、自分で時間割で行動するといった、時間の管理を自分でするようになっていくので、「知育時計」は役立ちそうですね。
知育時計のメリット4つ
お子さんに知育時計を与えた場合のメリットを4つご紹介します。
① 数字や時計の見方が身につく
お子さんが数字に興味を持ち始めると、知っている数字を読みたがるもの。
小さいうちは、数字の概念はわかっていなくても、数字の読み方順番など、興味が持てれば、見たまま情報をどんどん取り入れていきます。
興味を示した時に、そばに知育時計があれば、数字を見るきっかけ、時計に触れるきっかけを作れます。
知育時計は「長い針」「短い針」「秒針」などもあるので自然と時計の仕組みにも興味が持てたり、時計の見方にも慣れていきます。
すぐにはわからなくても、小さいうちから見慣れているのと、授業で習うときに初めて時計を見るのでは、抵抗感が違ってきますね。
② 自主性が育つ
「数字の○分になったらお片付けしようね」
「○時になったらお風呂に入ろうね」
など、小さいうち(3〜4歳ぐらい)から、時計を見る意識を向けてあげることで、自分から時計を意識できるようになる、スケジュール管理という感覚も身について、後の自主性の芽生えにもつながっていくでしょう。
③ 時計を見て時間を意識する習慣がつく
『時計がある』ということを知っている。
『時間を見る』といことを知っている。
そういう経験が、「今何時?」と時計を見る習慣へとつながっていきます。
自分から時間や時計を意識するようになるのも、小さいうちなら遊びの延長で取り組めます。
④ 自信と達成感が生まれる
自分で「○の数字のところまででお片付けをする」と決めた方が、ママやパパのペースで「もうご飯だから片付けて」というよりもお片付けがスムーズだったりします。
自分でというのが、小さいお子さんにとっては達成感を味わえるキーワードだったりするからです。
「時間通りにできたね!」
とママやパパに声をかけられる経験も、成功体験として自信につながっていきます。
知育時計の選び時のポイント
知育時計も、どこに設置するか?
どんな時に使うか?
どのくらいのお子さんが使うか?
などによっても選ぶときのポイントが違ってきますので、いくつかポイントをご紹介しますね。
使い方に合わせてタイプを選ぶ
お子さんが長く過ごす、リビングやダイニングなどに知育時計を置いておくと、日常生活の中で時計に目がいく機会が増えますね。そういう時は掛け時計がおすすめです。
小さいお子さんに興味を持たせたいなら、設置する高さを低めにしたり、メモリが大きめなものを選んだり、または置き型のものを選ぶのもいいかもしれません。
また玩具時計を用意して、本物の時計と合わせて時計に触れるのもおすすめです。

自分の手で針をクルクルと回したり、手に取る近さで数字を読めたりと視覚や手の感覚を使って楽しく学べます。
また、まだ数字が読めない小さいお子さんの知育玩具としても活躍しそうです。
どのような時に、知育時計が活躍しそうか、イメージしてみて選んでみるといいですね。
実用性と見やすさを考慮したデザインを
○時と△分が見分けやすい
○時と△分の見分けかたはなかなかお子さんには難しいポイントです。1〜12の時間の表記と、1目盛りごとに0〜59までの分の表記があるものなら、見分けがしやすくなるのでメモリの表記方法をチェックしてみてください。
24時間表記もついている
おこさんにはあまり馴染みがないかもしれませんが、意外と大人の会話では使われる「13時」やら「17時」などの24時間表記。「13時」の言葉に興味を持つお子さんもいるでしょう。
後に使うことにもなる24時間表記です。はじめから文字盤に24時までの表記されていれば、小さい頃は必要なくても、後々ひと目で理解ができて便利です。
理解を深めるなら短針・長針で色や太さが違うもの
時間・分の数字、お子さんにとっては、どこの何を見たらいいのかわかりにくいもの。
長針と○分の数字の色、短針と○時の数字の色がそれぞれ同じなら、迷いを少なくしてくれるでしょう。
お子さんに教えるときも、伝えやすいですよね。
シンプルなデザインは長く活躍できる
後々、お子さんが成長して、時計が読めるようになってしまえば、わかりやすさを求めたカラフルなデザインは必要なくなります。
お子さんが大きくなっても引き続きリビングで使う予定があるなら、シンプルなデザインのものを検討することもおすすめです。
この場合は、小さいお子さんにとっては、わかりにくいことがあかもしれないので、玩具の知育時計などと合わせて使うことを検討してみるのもいいかもしれません。
まとめ
お子さんの時間の感覚は、大人のようには身についていないものです。
自然に育っていくものというより、経験の中で少しずつ身につけていくもの。
と理解しておいた方がお互いのやり取りがスムーズです。
なので、日常生活の中でどれだけ大人が時間を意識する機会を作れるか?時計を見る習慣を作っていくか?
そんなことが大切になってきます。
お子さんの自主性を育てつつ、時間の感覚をつけるお助けアイテムとして、知育時計を使ってみるのも、「時間のお勉強」と肩の力を入れずに取り組めるのでおすすめです♪



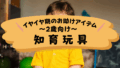
コメント