
「我が子に集中力をつけたいな〜!」
きっとママパパなら一度は頭をよぎるのではないでしょうか?
そんな時には、手軽に始められる知育玩具・「パズル」で集中力UPなんていうのはいかがですか?
パズルは何歳から始める?
結論から言えば、1歳ぐらいから始められます。
ただ何歳から始めた方がいい、というわけではありませんので、2歳から始めても、3歳から始めても遅いというわけではないのでご安心ください。
お子さんの興味や発達などは、それぞれ本当に違うので、目の前のお子さんの様子を見ながら判断するのが一番良いです。
例えば、0歳の赤ちゃんのうちは「手」全体を使ってものを掴んでいますが、だんだん指先が使えるようになってきて「つまむ」ということができるようになってきます。
まだ「つまむ」ことができないお子さんに、そのような玩具を与えても、上手く扱えないので、面白くないわけです。
興味を持たないわけですね。
なので、お子さんの発達に合った玩具が目の前にあるか、ないかによって、お子さんの興味は、大きく変わってしまうんです。
ですので、お子さんの今の発達にあった知育パズルが目の前にあれば、1歳ぐらいからでも十分パズルを楽しむことができるのです。
パズル知育の効果
パズルで遊ぶことは、知育に良いとされています。
子どもの成長に必要な能力をバランスよく育てる効果があるからです。
パズルをすることで、楽しく遊びながら、以下のような知育効果が期待できると言われています。
手先が器用になる
様々な形のパズルのパーツを、向きを変えたり、他のピースと合わせたり、カッチっとはめる動きが必要です。
手指先の細かい動きが自然と必要になるので、脳の働きの活性化にもいいと言われています。
また、手と目を上手に連携させる協調運動も育ちます。
これは将来の文字の書き取りや細かい作業の基礎になるので、とても大切な働きを、パズルという遊びの中で育てているとも言えますね。
集中力が養われる
パズルを完成させるには、ある程度の時間、集中しなければなりません。
好きなパズルに夢中になって取り組んで完成させているうちに、一つの作業をやり続けるという集中力を身につけることができます。
他の勉強や遊びにも役立ちますね。
最初は2〜3分しか集中力が続かなくても大丈夫。
繰り返し遊ぶうちに、だんだんパズルが完成する楽しさがわかってくるので、5分、10分と集中できる時間が延びていきます。
また、集中してパズルで遊ぶと記憶力の向上にもつながります。
完成した絵と見比べながら「このピースはどこかな?」と正しい場所を探したり、どんな形のピースを組み合わせると完成するのか?を少しずつ記憶していったりするので、記憶力の向上の効果が期待できるというわけです。
想像力が豊かになる
パズルでの遊びは、「完成したらこんな絵になるかな?」とできあがりを想像しながら、「このピースはここにはまりそう」と考える力が必要です。
完成系を想像して逆算しながら、色や形の違いを見分けたり、ピースの向きを考えたりするのです。
遊びながら、想像力を働かせたり、物の位置や形を理解する力も育てているのです。
論理的思考力が身につく
パズルを完成させる方法は、さまざまです。
私は、とりあえず角や端っこのパーツから埋めていきますが、お子さんたちは意外と中央にあるメインのキャラクターのピースから探していったりします。
頭の硬い私には、手が出せないやり方です^^。
何度も繰り返し遊んでいるお子さんなどは、手にしたパーツをどこに置くかを記憶していて、その記憶に沿ってパズルを完成させて行ったりもします。
「どうすれば完成させることができるか?」「自分のやりやすい方法は?」などを自然と考えてパズルに取り組んでいるのです。
まさに、論理的に思考を養うということを自然に遊びながら養っているというわけです。
「やり遂げる力」「自信」が身につく
パズルを完成させた時の達成感は大人でも気持ちの良いものです。
お子さんももちろん、パズルを完成させるたびに「やったー!できた!」という達成感を味わうことができるでしょう!
そしてその気持ちは、子どもの自信をぐんと高めます。
また、ママやパパの「完成したね!」「最後までできたね!」の声がけは、お子さんの「また頑張ってみよう」という気持ちにつながるでしょう。
そして、途中で諦めずに最後まで完成させる「やり遂げる経験」を何度も体験することで、お子さんの自信をさらに強めていけるでしょう。
失敗しない知育パズルの選び方ポイント
せっかくお子さんに、遊んでもらうために用意したパズルも、遊んでもらえなければ意味がなくなってしまいます。
そうならないための抑えたいポイントです。
子どもの成長に合わせて選ぶ
パズルに表示されている対象年齢はあくまで、目安です。
お子さんの成長には個人差があるのを考慮して、まずは「ちょっと簡単かな?」と思うレベルから始めてOKです。
だいじなのは「できた!」という達成感。
お子さんに達成感を味わってもらうにはどれがいいかな?
という視点で選んでみましょう。
子どもの好きなものを選ぶ
お子さんの好きな題材のものから選ぶのもおすすめです。
なにしろ、まずは興味を持ってもらうことが、大事ですから。
「アンパンマンなどのキャラクターが好き?」それとも「乗り物?」「動物?」
お子さんが好きなものだと、興味を示して集中して取り組んでくれますね。
安全性(STマーク・誤飲防止)をチェックする
小さなお子さんが使うパズルは、安全性の確認も必要です。
STマークがついているパズルは、14歳以下の子ども向けに安全基準をクリアしたおもちゃです。
特に小さい1〜3歳の子どもは何でも口に入れると思って、誤飲を防ぐためにも、直径4cm未満のものは、避けるようにしましょう。
また、パズルに限らずですが、遊んでいるお子さんから目を離さないのも大切ですね。
【年齢別の目安】パズルの種類とピース数
ここにある年齢は目安です。
パズルをしたことがあるか?どのくらいの頻度でやったことがあるか?などでもお子さんの取り組み方は違っています。
お子さんの様子を見ながら参考になさってください。
1歳:知育パズルデビューは型はめパズルから
1〜1歳半ぐらいの子お子さんは、まだ指先の使い方を覚えているところです。
パズル遊びのスタートには、手全体でつかめる大きくて厚みのあるピースの型はめパズルがおすすめです。
パズルとはちょっとイメージが違いますが、穴が丸型の「ポットン落とし」は上下左右の向きに関係なくはめ込めるので、とにかく赤ちゃんたちは無心によく遊びます。
手作りのポットン落としは、保育園でも大人気のおもちゃでした!
そして、型はめのパズルは、保育園での遊びの様子を見ていて、6面の色々な型があるものより、数は少ないのですが、6個ぐらいのパーツをはめるようなものの方が、1歳前後の小さいお子さんにはわかりやすく、よく遊んでいた印象です。
つまみがついているパズルも、つまむことが楽しくなってきたパズルデビューのお子さんには、ぴったりです。
2歳:パズルで学びの基礎固め
初めてパズルをする子には1〜10ピース程度の板パズルがおすすめです。
慣れてきたら、少しずつピース数を増やしていくのがパズル好きにするコツです。
この時期のパズル遊びでは、1つずつのピースを見て「これはどこかな?」と、見て比べて…とよく見る力、覚える力、問題を解決する力など、これから勉強するのに必要になる基礎の力がどんどん育っていきます。
3・4歳:30〜50ピースに挑戦!一人で取り組む力もついてくる
3歳ぐらいになってくると、空間を理解する力や筋道立てて考える力・想像する力がついてくるので、その成長にとても役立ってきます。
パズルの完成図を頭に描きながら、ピースの色や絵、形などを手がかりに、作業するようになってくるのです。
それが、論理的に考える力につながっていきます。
また、4歳ぐらいは、ママやパパの手助けなしに、「全部一人で完成できた!」という気持ちも生まれてきます。
なのでこのくらいの時期には、ピースの数というより、一人でできる!という達成感を味わわせてあげるといいですね。
5歳以上:立体パズルや高難度パズルにも挑戦
この頃になると、少し時間をかけて取り組む数の多いパズルにも挑戦できるようになり、取り組み方も大きく変わってきます。
目の前のピースをはめるだけでなく、先のことを見通しながら、どうすれば効率よく完成できるかを考える力も身についてきます。
パズル遊びを通して、問題解決力・長い時間集中する力・創造力など、将来にも役立つ力をどんどん発達させていくことができます。
パズル知育を成功させるサポート方法
子どもが集中している時は話しかけずに見守る
お子さんが集中している最中に褒めてしまうと、せっかくの集中が途絶えてしまいます。
話しかけたい気持ちをグッと堪えて、見守ってあげましょう。
褒めるタイミングは、完成させてお子さんがホッとした表情を見せた時。
「よ〜く集中してたね〜!」と具体的に。
取り組む姿勢や過程を褒める
パズルを完成させたことは素晴らしいことなのですが、それよりも、お子さんの取り組む姿勢や、過程を言葉にしてあげることをお勧めします。
「最後まで諦めなかったね!」
「じっくり考えられたね」などです。
ついやってしまいがちなのですが、「完成できてえらかったね!」みたいな、できた、できないの評価の声掛けは避けた方がいいです。
なぜかというと、「もし出来なかったらすごくない…だから初めからやらない」という選択をしてしまうタイプのお子さんもいるからです。
とはいえ褒められたらお子さんは皆嬉しいですから、あまり固く考えずに頭の片隅のどこかにでも入れておいいただけたらなぁと思っています^^。
「出来た!」の経験は、自己肯定感を高め「チャレンジできる脳」を育てると言われています。
少しの時間でも集中していたら、その行動を認めてあげてくださいね。
子どもが集中しやすい環境作り
せっかくパズルをやり始めたら、テレビを消したり、パズル以外のおもちゃをかたづける。
視界に入る場所や手が届くところに気を引くものを置かない…など、気が散る要素を取り除くなど、お子さんの環境を配慮してあげることも大切ですね。
まとめ
いかがでしたか?
知育玩具としてのパズル遊びをお勧めする理由はなんといっても集中力!
ちょっとした配慮で、楽しいパズル遊びの時間で集中力をアップできますね!
ポイントは3つ
- お子さんに成長と経験にあったパズルを選ぶ
- お子さんの好きなものをとっかかりにしてパズルを選ぶ
- お子さんの集中を妨げない環境づくり
気軽に始められる知育の種まき、「パズル遊び」で集中する楽しさをぜひ味わわせてあげてみてくださいね♪
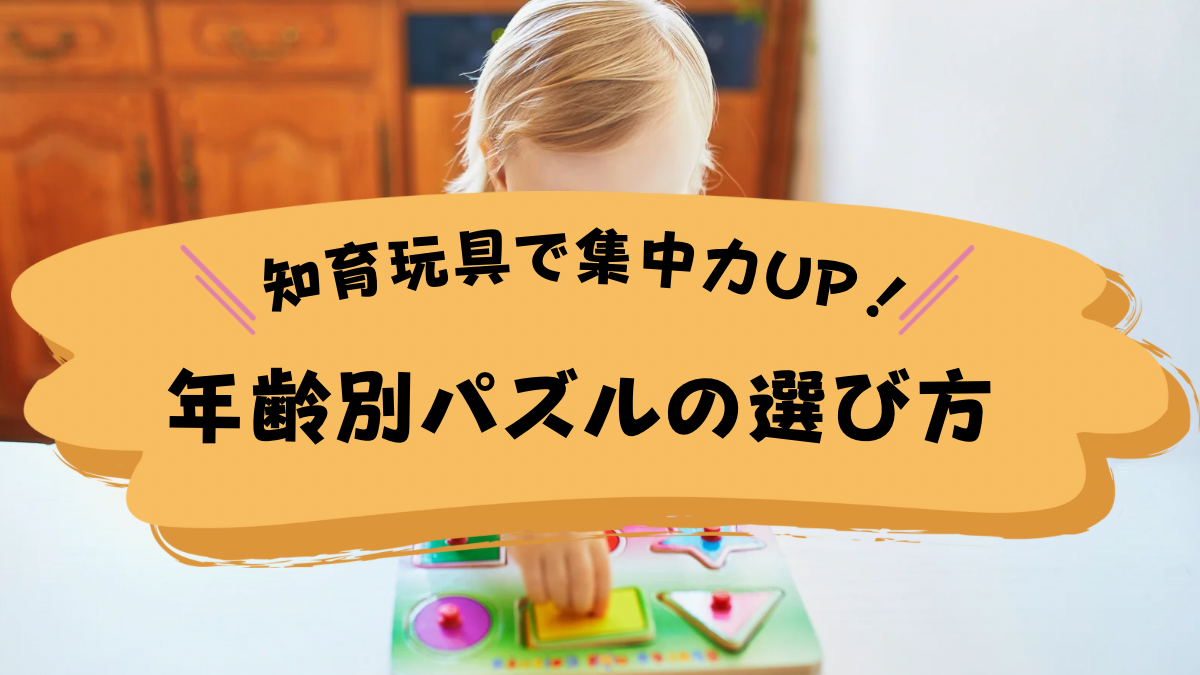




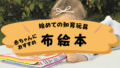
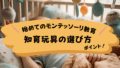
コメント